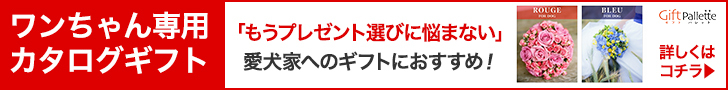闘病記の意義(2/2)

本記事では、闘病記のスタイルについて触れましょう。
前記事にも書きましたが、我々にとって闘病記は貴重な情報源です。
恐らく、大多数の飼い主にとって闘病記は、医学書や医学論文を読むよりも、ずっと現実的で役に立つもののように思います。
●
本サイトにおける闘病記は、突然愛犬の病気に直面した飼い主の方々が、これから愛犬の病気に立ち向かうおうという時の参考になるよう、なるべく客観的に書くことを心がけています。
※尚、ここでいう闘病記とは、主に重病の場合のものであり、愛犬の命を賭けた(多くの場合には最後の)闘病を指します。
【目次】
犬の闘病は重篤化しがち

犬(および動物一般)は口がきけないために、病気が発覚するのが遅れがちで、判明した段階でかなり進行していることが多いようです。通常の場合、病気の発症時点では、飼い主の側に病気に対する知識がほとんど無いと言って良いでしょう。
突然に危険な状態からスタートする愛犬の闘病は、飼い主にとって、きっと戸惑いと恐れしかなでしょう。最初は筆者もそうでした。
●
急性疾患の場合は、早ければ2、3日の内に決着がつきます。
決着と言うのは、死亡を意味するとおもわれるかもしれませんが、そうではありません。重篤な急性疾患の場合は、適切な治療によって回復する可能性があるのです。
慢性疾患と違って、原因を突き止めることができれば、数日の内に全快に近い回復を示すこともあります。限られた時間の中で、原因とそれに応じた治療法を探せるかどうかが勝負となります。
●
慢性疾患の場合は、残念ながら全快する可能性は低いように思います。
しかしながら、やはり適切な治療を早期にはじめることで、余命が飛躍的に延びることが良くあります。
余命3か月と告げられた犬が、2年も3年も生きている例は沢山あります。
●
これらのことを指して、奇跡と言う人たちがいますが、一般的に言われる”奇跡”とは、少し趣が違うように思います。急性疾患も慢性疾患も、最適な治療法を探し当てることさえできれば、それは奇跡ではなく、現実に起きることなのです。
敢えて奇跡と言う言葉を使うならば、『奇跡的な確率で病気の原因を探し当てたことで、必然的に病気が快方に向かった』という言い方が良いように思います。
選択肢は必ず他にもある

犬の闘病は多くの場合、はじめに受診した病院(ほとんどの場合は、掛かりつけの主治医であることでしょう)の判断で闘病が進んで行くことになると思われます。
それ以外の選択肢というのは、獣医師からはなかなか提示もされないしでしょうし、飼い主には思いつきもしないことでしょう。
しかし、そこで一歩踏みとどまって、考えていただきたいのです。
●
例えば、主治医以外の医師にも治療についての意見を聞くセカンドオピニオンと、その病気の専門医のいる病院で治療を受ける、二次診療という方法があります。
我が家のピーチーは、それによって2度命を救われました。
(細かくは次項に記します)
●
このように、闘病に別の選択肢を示してくれるのが、他の飼い主が書き残してくれた闘病期だと思うのです。誰かの過去の経験を、愛犬の治療に活かすことができれば、無駄な試行錯誤の時間を省くことができますし、飼い主と主治医の間で考えるよりも、ずっと選択肢の幅が広がります。
闘病記のスタイル

闘病記には幾つかのスタイルがありますが、大きくは下記の3つです。
1.
日付に沿って、日記のように書いていくオーソドックスなスタイル。
当サイトでは、検査結果などの表記の仕方を統一することで、読みやすくすることを心がけます。
2.
治療方法や経過など、重要なことだけを抜き出して、コラムのように簡潔にまとめるスタイル。全体を見通してから構成をする必要があるため、文章としての難易度が高いくなります。
3.
上記1を軸にして、後日に作者が当時の思いや反省点を、コメントとして書き加えるスタイル。分かりやすい代わりに、執筆作業に時間がかかります。
●
※その他、エッセイの中に闘病記の要素を織り込んだものもありますが、当サイトではそれはエッセイに分類をしています。
例えば、筆者の愛犬ピーチーの場合は

筆者の愛犬ピーチーは、14歳と7か月で天国に行ってしまいましたが、それまでの間に2度、死の縁を覗くほどの重い病気を経験しました。
幸いにも筆者とピーチーは、最初にその局面に遭遇した際に、主治医によって”高度医療”という選択肢が示され、それによって命を拾いました。もしもそれがなければ、ピーチーは11歳の頃に天国に旅立っていたことでしょう。
●
これまでに、ピーチーが死の淵を覗いたのは2回と書きましたが、実際にはそれに近い状態が更に2度ありました。そして5回目が、本当に最後の闘いとなりました。
発生順に書くと下記のようになります。
1回目:11歳のとき
急性膵炎を発症。一時回復するも、その直後に胆管閉塞を併発。
2回目:13歳と9か月のとき
癲癇の重積発作。一晩で7回の発作+病院での処置中に1回発症。
3回目:13歳と11か月のとき
劇症肝炎。ステロイドの大量投与によって、奇跡的に回復。
4回目:14歳と1か月のとき
ステロイドの減薬中に再度の肝炎症状。免疫抑制剤によって難を逃れる。
5回目:14歳と7か月のとき
微かな呼吸の異常から、撮影したレントゲンで肺に影が見つかる。
肺癌の疑いあり。
その後、急激に病状が悪化し、20日後に他界。
●
1回目:急性膵炎+胆管閉塞の闘病記はこちらに
3回目:劇症肝炎の闘病記はこちらに
5回目:見取り+肺がんの闘病記はこちらに
ケーススタディとしての闘病記

本記事以降、7記事に渡って、ピーチーの闘病を連載ししようと思います。
まずは闘病記を読む前に知っていただきたいことを、本話に続いて3話に渡ってご紹介し、次いで闘病記(急性膵炎からの胆管閉塞)を、コラム(またはドキュメンタリー)のスタイルで4話連載します。
多くの方の闘病の参考になるように、ケーススタディとなるように記述していきます。ピーチーの闘病記の後は、他の犬たちの闘病について順次公開する予定です。
どうかこの闘病記が、多くの飼い主さんたちのお役にたつことを祈って。
――闘病記の意義(2/2)おわり――
――闘病の中にもある効率と戦略(全3話)につづく――
文:高栖匡躬
▶プロフィール
▶ 作者の一言
▶ 高栖 匡躬:犬の記事 ご紹介
▶ 高栖 匡躬:猫の記事 ご紹介
Follow @peachy_love
――次話・闘病、新しい視点(1/3)――
次話は新シリーズです
闘病記を読むと、奇跡的に治るという表現に時々出会います。
しかし奇跡は、待っていて起きるものではありません。
奇跡が起きる確率は、努力で上げることができます。
医師まかせにせず、とにかく情報を集めて分析する事です。
その中に、もしかすると答えがあるかもしれません。
――前話――
犬が病気になった時、幾ら探しても、役に立つ医療情報が見つかりませんでした。
通り一辺倒だったり、逆に専門的過ぎたり。
どれもこれも、現実的ではないのです。
そんな中、飼い主が書いた闘病記に行き当りました。
動物医療の専門家ではない、普通の飼い主が書いた闘病記です。
そこからは、本当に色々な事を教わりました。
●
この記事は、下記のまとめ読みでも読むことが出来ます。
●
闘病は視点を変えて
視点を変えれば、闘病も変わる――
愛犬の闘病で悩む飼い主さんは多い。
それは見えない不安が、心にのしかかるから。
これからどうなる? いつまで続く? 医療費は?
見えないものは仕方ない。しかし、見えているものはある。
不安に怯えるのではく、どうか前向きに。
●
臨床現場から見た、良い獣医師の選び方
”良い”獣医師選びは、飼い主の責任でもあります。
目的は常に動物の病気を治すこと。
そのために獣医師は何をすべきか?
そう考えると、自然に”良い獣医師”とは何かが分かってきます。
現場を知るからこそ出来るアドバイス。
獣医師選びの方法、教えます
動物病院は沢山あって、どこが良いか迷いますよね。
獣医師次第で治らないと思った病気が治ったり、治る病気が治らなかったり。
経験した方も多いはず。
どうやって選びます。
『オタ福の語り部屋』の主宰者、オタ福さんに聞きました。