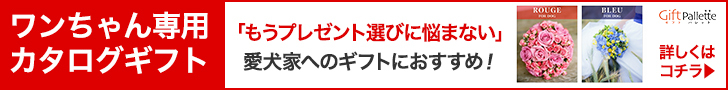チョコラッの闘病記 第2章(3/6)

本記事は長期連載の1部。そしてチョコラッは3年目(2019年6月)を迎えて生存中です。
難病であっても希望を持ち続けたいと願う、飼い主の思いで書かれた闘病記です。
初回記事はこちらです。チョコラッの闘病記 1話
ペットに貧血の症状が現れ改善しない|非再生性免疫介在性貧血と診断された|治る見込みは?|治療法は?|どんな闘病になるのか心配|免疫系疾患の難しさを実感している|経験者の体験談が聞きたい
11月16日 PCV(血球容積)の推移
昨日はチョコラッの病院。
貧血を表す数値
※通常の値は37〜
前回は19%だったから、少し上がったけど、今までの推移から見ると上がったと言うよりは20前後を横ばいと言った方が正しいかも。
●
Hb(ヘモグロビン濃度)は13〜が標準値だけど、チョコラッは7辺りで変わらず。
ヘルニアをもう一度よく診てもらい、腹壁ヘルニア・鼠径ヘルニア・会陰(直腸)ヘルニアを現在患っており、腹壁〜鼠径部(お腹から脚の付け根の筋)にかけての隙間は広がりつつある。
●
「ヘルニア(脱腸)なのに圧迫排尿するから、内部で出血して貧血してるのでは?」と
ずっと考えてた疑問を投げかけると、
「その場合は便がタール状の黒色になるはずだし、腹部エコーでも炎症が診られない。
それに通常ヘルニアでここまでの貧血にはならない」と。
医師はヘルニアと貧血は別問題で考えてるみたい。
今後の治療

前回調べた骨髄(造血)検査の結果はまだ出てなかった。
今後の治療法は、
○免疫介在性溶血性貧血の薬を点滴。
○変化が無いようなら、他の薬を投薬。
○入院期間未定。
免疫介在性溶血性貧血と断定はしないけど、消去法で考えて、免疫介在性溶血性貧血(免疫異常で自己の赤血球を壊してしまう病気)の可能性が一番高い。
輸血は本人の体調を診ながらだけど、PCV10%を切る様なら実施。
だから引き続き、献血犬を探さなくてはいけない。
●
今回、納得いくまで医師と話が出来、信頼出来ると夫婦で判断したので、セカンドオピニオンは取らず、このまま今の医師にお願いすることにしました。
今の病院かなり大型だし救急医療センター兼ねて24時間体制だし、下手に移らない方が良いだろうと考える。
今日の様子は
ご心配おかけしますが、幸いチョコラッは傍目には貧血と分からないくらいに、今は元気!
過去にも沢山の入院や手術を乗り越えて、復活してきてくれた子だから、
今回も家族皆んなで協力して必ず乗り切りたいと思いますので、見守ってやって下さい。m(__)m
――【非再生性免疫介在性貧血】最終検査結果まで(3/6)・つづく――
文:らぶプー
▶らぶプー:他の作品一覧
――次話――
最終検査結果が出て、病名は免疫介在性溶血性貧血にほぼ確定という段階に来ます。しかし、確定診断は難しい。
――前話――
低いながらも一定水準を保っていたはPCV(血球容積)が下がります。
医師からは追加の精密検査の話が。
●
この記事は、下記のまとめ読みでもご覧になれます。
この記事は、下記の週刊Withdog&Withcatに掲載されています。
●
――この章の最初の記事です――
一応の確定診断。免疫介在性溶血性貧血をネットで調べるたびに、生存率などの現実を突きつけられるのでした。
――この連載の最初の記事です――
はじめの症状は食欲不振でした。貧血が判明し、病名を探っていくところからこの闘病記が始まります。闘病記を書く理由についても語られます。
おすすめの闘病記です
愛犬を看取る、家族のお話。
ペットと暮らす者なら誰もが通る道だけれど、少しずつ違う道。
色々な選択肢があって、正解は一つではない。
わが家なりの送り方って何?
『ラフと歩く日々』の続編です。
医学書や論文を読むよりも現実的な情報源
愛犬が病気になった時、役に立つ医療情報はなかなか見つかりません。
通り一辺倒だったり、逆に専門的過ぎたり。
どれもこれも、現実的ではないのです。
そんなときには、飼い主が書いた闘病記を読むのが良いでしょう。
動物医療の専門家ではない、普通の飼い主が書いた闘病記が、様々なことを教えてくれるものです。
出典
※本記事は著作者の許可を得て、下記のブログを元に再構成されたものです。