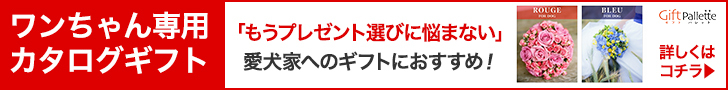チョコラッの闘病記 第4章(13/22)

本記事は長期連載の1部。そしてチョコラッは3年目(2019年6月)を迎えて生存中です。
難病であっても希望を持ち続けたいと願う、飼い主の思いで書かれた闘病記です。
初回記事はこちらです。チョコラッの闘病記 1話
ペットに貧血の症状が現れ改善しない|非再生性免疫介在性貧血と診断された|治る見込みは?|治療法は?|どんな闘病になるのか心配|免疫系疾患の難しさを実感している|経験者の体験談が聞きたい
8月12日 また貧血が進んでいた
昨日、チョコラッの血液検査に行きました。
貧血が進んでいました。
1週間でかなり落ちてしまった。
6月8日からの推移を見ると――
やはり徐々にに落ちています。
●
減っていく薬の選択肢
医師には今の薬(3/30に開始したアトピカ)が効かなくなってきた可能性が高いと言われました。
昨年秋に非再生性免疫介在性貧血になり、プレドニン効かず、セルセプト追加で安定するもセルセプト効かなくなり、ガンマガード入れて(点滴)時間稼ぎして、アトピカで安定。
今はアトピカもダメ。
●
残る選択肢はお薬ではアザチオプリンとレフルノミド。
これは5〜8割の確率で深刻な副作用が出る。
副作用とは、肝障害と骨髄抑制。
あと、癌になる可能性が上がる。
肝障害は最悪死ぬよね?
骨髄抑制も一気に貧血が進んで死んじゃう。
●
血液検査をこまめにして、少量から始めるから肝障害を起こす前に服薬を中止すると聞いたけど、少量じゃ効かないかも。
しかもお薬の効果が見られるのは1〜4ヶ月後。
結構窮地に立たされてしまった。(´;ω;`)
楽観的になんてなれないよ

チョコラッは今はまだ元気元気なんだけど、貧血が進めばどんどん具合が悪くなり何もしなければ死んじゃう。
でも、治療するお薬を与えることによって死ぬかもしれない。
2〜5割は副作用出ないって楽観的に考えられればいいのに。
●
今はまだ新しいお薬は試してなくて、昨日からアトピカを2倍量に増やしました。
2倍量で1週間後にまた検査して、良くなってたら新しい薬は使わない。
扉の写真は、動物病院で診察終わってニコニコチョコラッ。
良くなったらいいな。
皆様、応援いつもありがとうございます。
今、少し苦しいときなので、良くなるよう願って頂けたら嬉しいです。
●
これは、パパとお手手繋いで寝るチョコラッ
(何故か寝るときもお目目閉じられないの)

最近は、あの晩以降もやっぱり呼吸が早めな気がするな
本人元気なんだけど
――【非再生性免疫介在性貧血】1年生存率5割って(13/22)・つづく――
文:らぶプー
▶らぶプー:他の作品一覧
――次話――
『スライドの赤血球を見ても大分壊れてます』
それは、顕微鏡を覗いた医師の言葉。
過去の検査結果を見直して、免疫抑制剤が効いていないことを再確認する飼い主。
――見た目は元気なのになあ。
倍に増えた薬に、望みを託す飼い主なのでした。
――前話――
夜中、ふと目が覚めると、チョコラッの呼吸が随分と速い。
心配であれこれ、する飼い主。
しかし、どうやら暑かっただけのようだ。
病気になると、薬の副作用も含めて色々なことが起きるもの。
●
この記事は、下記のまとめ読みでもご覧になれます。
この記事は、下記の週刊Withdog&Withcatに掲載されています。
●
――この章の最初の記事です――
血液検査の結果は良くない。薬の効果がなかなか安定しない。
有効成分の血中濃度と効果はまた別だし、医師もまだ正確な判断が出来ない。
体調が良いのは救いなのだけれど……
頭の中を、不安がグルグル回る。
――この連載の最初の記事です――
この病気は、自己免疫不全で起きるもの。
自分の免疫が、自分の体を攻撃し始めるのです。
病原菌やウィルスが見つかるわけでもなく、CTやMRIにも病変が映りません。
なんとなく調子が悪い……
病院に行っても原因不明。
しかし、状況は悪化していく。
何故――
チョコラッの闘病記は、そんな飼い主さんの記録です。
まずは病名が確定するまでのお話から。
●
ステロイド、免疫抑制剤の闘病記
ステロイドの減薬|体験談と闘病記
ステロイド剤は一般的な薬であるにも関わらず、必要以上に嫌われているように感じます。その原因として、適切な使用方法が行われておらず、そのために無用の副作用を被る場合が多いのだと想像できます。
実際に飼い主さんたちが書いた体験談(闘病記)を読むと、動物医療の専門家である獣医師でさえ、ステロイド剤の功罪を良く知らないで使っている場合が多いように思えるのです。
免疫抑制剤|体験談と闘病記
愛犬ピーチーの体験談、今回は免疫抑制剤です。
ステロイド剤から免疫抑制剤への切替は簡単ではありませんでした。
今回はその難しさの実例を。
犬の原因不明の病気の影には、自己免疫不全があるように思います。
実は多くの犬が、無縁でないのでは?
●
出典
※本記事は著作者の許可を得て、下記のブログを元に再構成されたものです。