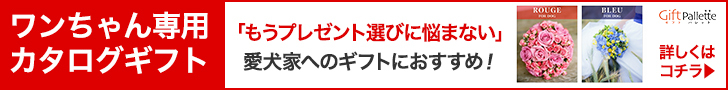ろくすけの闘病記:癲癇(てんかん)2話

ろくすけ、てんかん確定の巻、です。 あの頃に戻って心配してる私って…
こんな方に:愛犬が癲癇(てんかん)|突然の発作でどうしていいか分からない|この先の経過が不安|他の飼い主さんはどうしているの?|経験者の話を聞きたい<
2015年5月18日 午前2時すぎ 二回目の発作
ろくすけ、とうとう二回目の発作(涙)
症状と経過は初回とほぼ同じ。
一度発症するとその後の発作も同じ症状になることが多いらしい。
発作時間もほぼ同じ。
●
痙攣は3分ほどだった。今回はちゃんと時計を見る余裕がもてた。
その後は前回と同じように、「ワオーン ワオーン」と1分ほど。
それから、立たない足で歩こうとして倒れ 歩こうとして倒れてを繰り返しながらの徘徊がスタートした。
●
夫が外に連れ出し、暗闇の中を1時間ほど、家の周りをひたすら歩く歩く……
家に戻っても、ひたすら歩く歩く……
辛いのに、歩かざるを得ないのか?
取りつかれて歩かされているように見える。
ただ今回もしばらくしたらフードを食べた。
最初はいつもの半分を与え、徐々に追加していった。結局いつもの量に到達。
もちろん、脱水しないよう、水でふやかして。
●
そして今日も休むことがないまま、朝いちで病院へ。
かかりつけの病院は、緊急でない場合は番号を取って、順番が来たら電話連絡をくれるので、病院嫌いのろくすけを病院内で待たせることがなく、助かっている。
ただ優しい獣医の先生は、夜中まで診察されることも多くて、いつ寝てるのかと先生のことが心配になったりする。
薬の名はゾニサミド

診察後にはやはり「てんかん」との診断で、抗てんかん薬を処方してもらった。
その名も『ゾニサミド』だ。
――ぞ・に・さ・み・ど。
――なんか、おどろおどろしい名。
上の写真がその『ゾニサミド』100mg 1日1錠(1/2×2回)
●
てんかん薬の中でも比較的副作用が少ないそうだが、しばらくは朦朧とするそうで、見守っておくようにとのことだった。
ろくすけの先生の方針は「薬は最小限に」とのこと。
先生、信頼しています!よろしくお願いします!
●
ワンちゃんによっては薬を飲んでもらうのが大変だったりするようだが、食いしん坊のろくすけは、フードの中に薬をしのばせておけば楽勝なので、本当に助かっている。
以前共に暮らしてたトイプードルは、上手にフードと薬を分けて残すし、口に入れようとすると暴れるしで、大変だった。
――可愛かったけど(^^)
●
帰宅後、ろくすけはフードに混ぜたゾニサミドを難なくペロリ。
そしてしばらくすると、足に全く力が入らなくなった。薬が効き始めたようだ。
体重16キロを持ち上げるようにしてハウスに連れていくと、やっと寝た。
今はとにかく睡眠をとって、疲れを癒してほしいと願う。
――突然の発作に驚いた(2/6)つづく――
作:きづあすか
▶きづあすか:作品一覧
Follow @KIZASKA
――次話――
2回目発作から更に約2か月。3度目の発作。
――2か月周期か?
頭を起こそうとした瞬間だった。
混乱してかあちゃんの手を本噛み!
「痛!」
それからは、前回同様歩く、歩く、歩く……
薬の処方が増量になった。
次の発作も来るのかなあ?
怖いなぁ……
――前話――
深夜、突然の癲癇初発作
痙攣が止まると、吠えた。
「ワオーン ワオーン ワオーン」
1分以上も。
本人は何が起きたのかわからず、パニック状態なのだ。
そして、よたよたと起き上がると、
歩く、歩く、歩く
これが、ろくすけの闘病の始まりでした。
●
この記事は、下記のまとめ読みでもご覧になれます。
この記事は、下記の週刊Withdog&Withcatに掲載されています。
●
――この章の1話目です――
今日から、きずあすかさんの愛犬、ろくすけ君の闘病記を連載します。
病名は癲癇。ある日突然に発症しました。
「あの病態は、飼い主の心を乱します」
その言葉に、経験者の方は皆うなずくことでしょう。
初回は、闘病記を残す理由です。
●
闘病を考える
愛犬の闘病で悩む飼い主さんは多い。
それは見えない不安が、心にのしかかるから。
これからどうなる? いつまで続く? 医療費は?
見えないものは仕方ない。しかし、見えているものはある。
不安に怯えるのではく、どうか前向きに。
●
闘病記のヒント
闘病の奇跡は呼び込むもの
闘病記を読むと、奇跡的に治るという表現に時々出会います。
しかし奇跡は、待っていて起きるものではありません。
奇跡が起きる確率は、努力で上げることができます。
医師まかせにせず、とにかく情報を集めて分析する事です。
その中に、もしかすると答えがあるかもしれません。
セカンドオピニオンと二次診療
街の獣医師の技術と経験には大きな差があります。知識にも差があります。
なぜなら街の獣医師は、内科医であり、外科医であり、犬や猫だけでなく、ネズミも鳥も診察するのが役割です。病気ごとの専門医ではないのです。
セカンドオピニオンと二次診療は、街の獣医師の足りない部分を埋める、重要な手段と言えます。
●
出典
※本記事は著作者の許可を得て、下記のブログを元に再構成されたものです。