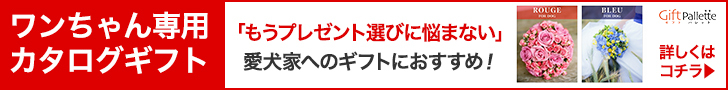ろくすけの闘病記:癲癇(てんかん)4話
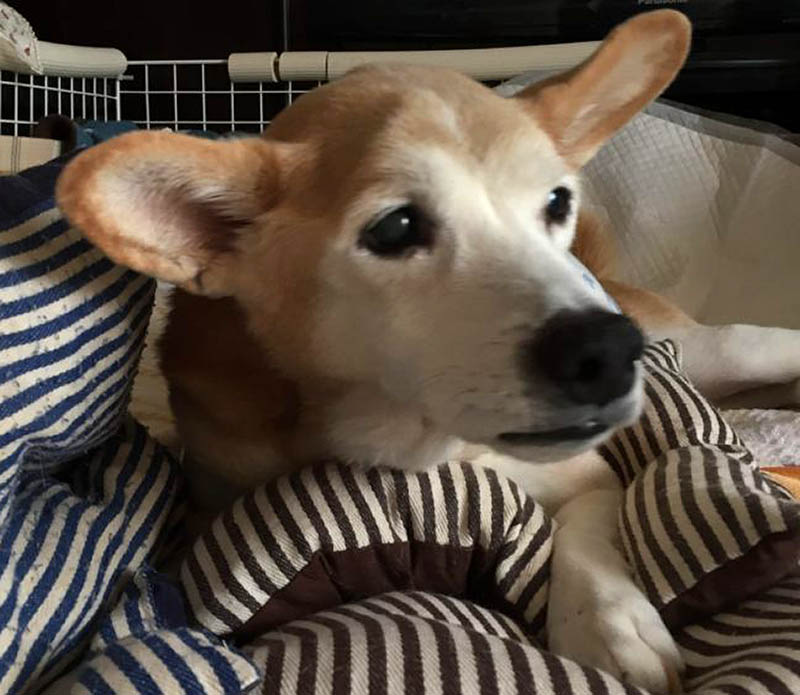
2015年8月26日 午後2時半
初めての昼の発作。
たまたま傍にいたので気づくことができたのだ よかった。
深夜の発作と違い、静かな痙攣、静かな発作。
●
痙攣時間は1分半から2分弱と短め。
短かったし、吠えることもなく終わったのも初めて。
失禁もなくよだれだけ。
昼に発症したことがショックはあるが、幸いにも軽い発作だったので、動揺はなかった。
●
手を噛まれないように、首の後ろからクッションを入れて頭を高くする。
頭を高くすることは有効だと、噂で聞いたので早速試してみたのだ。
すると――、なんととくすけ、目が見えたようになり、立ち上がろうとする。
――よしこれ採用!
●
しかしながら、足自身の力はなくて立てない。
とにかく、これが徘徊の始まりのサインなので、急ぎサークルをセッティング。
徘徊は今までと違い、パワーもなく、時間も短くて、そのまま床に倒れこんでからウトウトし始めた。
病院へ電話

夕方5時になり病院へ電話。
今回は軽度であること、通常に戻りつつあることを伝えると、様子を見ることになった。
明日は病院が休みだが、何かあれば折り返し先生が連絡くれるとのこと
あぁ、ありがたい。
●
落ち着いてきたので、ろくすけをサークルから出してみると、水をがぶのみ。
ブロッコリーも食べた。
それご飯だ! はい完食!
食いしん坊はやはり、食いしん坊であり続けてほしい。
ただ、うんちもおしっこもしないので、今晩はおむつだな。
――と、思ったら、外に出すやいなや 大量のおしっこ。
うんちはしないけど、ま、いいか。
これで落ち着いて夜、寝てくれれば。
●
ところで、ろくすけの場合、全て睡眠中の発作であり、発作前の兆候というのはない。
というより 私も寝ている時間なので発作直前の様子はわからないのである。
ただ発作が起きるようになってからは、体をびくっびくっと震わせる、チックのような症状や、口をくちゃくちゃさせる(チューインガム発作とういらしい)動作が頻繁になった。
これがあったから即発作 というのはないのだけど
調子は良くないんだろうな
●
てんかんには特効薬がないのが悲しい。
でも病気と付き合っていくことで、ろくすけとの濃密な時間が増えたことは確かだ。
悪いことばかりではないのかな。
――突然の発作に驚いた(4/6)つづく――
作:きづあすか
▶きづあすか:作品一覧
Follow @KIZASKA
――次話――
深夜3時、久しぶりの発作。
防水シートがあるから、失禁してもへっちゃらだ。
徘徊に備えサークルを用意する。
と、ろくすけはその中で、ぐるぐるぐる。
気付け薬のごはん。
――はい、完食!
慣れてくる。驚かなくなる。
でも、発作の間隔は短くなった――
――前話――
2回目発作から更に約2か月。3度目の発作。
――2か月周期か?
頭を起こそうとした瞬間だった。
混乱してかあちゃんの手を本噛み!
「痛!」
それからは、前回同様歩く、歩く、歩く……
薬の処方が増量になった。
次の発作も来るのかなあ?
怖いなぁ……
●
この記事は、下記のまとめ読みでもご覧になれます。
この記事は、下記の週刊Withdog&Withcatに掲載されています。
●
――この章の1話目です――
深夜、突然の癲癇初発作
痙攣が止まると、吠えた。
「ワオーン ワオーン ワオーン」
1分以上も。
本人は何が起きたのかわからず、パニック状態なのだ。
そして、よたよたと起き上がると、
歩く、歩く、歩く
これが、ろくすけの闘病の始まりでした。
●
――この連載の第1話です――
今日から、きずあすかさんの愛犬、ろくすけ君の闘病記を連載します。
病名は癲癇。ある日突然に発症しました。
「あの病態は、飼い主の心を乱します」
その言葉に、経験者の方は皆うなずくことでしょう。
初回は、闘病記を残す理由です。
●
闘病を考える
愛犬の闘病で悩む飼い主さんは多い。
それは見えない不安が、心にのしかかるから。
これからどうなる? いつまで続く? 医療費は?
見えないものは仕方ない。しかし、見えているものはある。
不安に怯えるのではく、どうか前向きに。
●
闘病記のヒント
闘病の奇跡は呼び込むもの
闘病記を読むと、奇跡的に治るという表現に時々出会います。
しかし奇跡は、待っていて起きるものではありません。
奇跡が起きる確率は、努力で上げることができます。
医師まかせにせず、とにかく情報を集めて分析する事です。
その中に、もしかすると答えがあるかもしれません。
セカンドオピニオンと二次診療
街の獣医師の技術と経験には大きな差があります。知識にも差があります。
なぜなら街の獣医師は、内科医であり、外科医であり、犬や猫だけでなく、ネズミも鳥も診察するのが役割です。病気ごとの専門医ではないのです。
セカンドオピニオンと二次診療は、街の獣医師の足りない部分を埋める、重要な手段と言えます。
●
出典
※本記事は著作者の許可を得て、下記のブログを元に再構成されたものです。