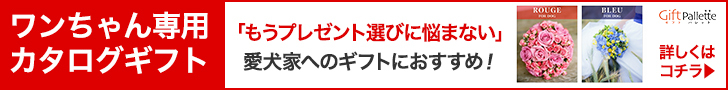ろくすけの闘病記:癲癇(てんかん)5話

2015年9月29日 午後3時 深夜の発作
――2015年9月29日 午前3時――
久しぶりの午前3時の発作。
やっぱり深夜の発作の方ががメインか?
痙攣時間は3分半から4分。
口からの泡、よだれはあるが、おしっこは少し漏れた程度。
●
実は一緒に寝るとき 人間の介護などで使う防水シーツを使っている。
なのでろくすけがどんなに失禁しても、へっちゃらなのだ。
人間に対しても犬に対しても 介護の時いちばん大事なのは、介護する側の心の余裕。
今の時代、いろいろなグッズがあるので大いに利用しないとね。
●
そして、発作後の定番。一通り吠えてからの、徘徊スタート。
今回のワオンワオンは時間にして1分程度でいつもより少し長かった。
さてサークルを出そう――
そう思った時に、ろくすけが色々なところにぶち当たりながら、窓とテーブルの間に挟まって動けなくなった。ちょうどいいぞ その間に急いでサークルセット。
サークルが倒れないように大きなクッションをサークルのまわりに並べる。
さあ、サークルにおいで。 ろくすけ。
●
不安そうに、時々「ふーん」といいながら、ぐるぐるぐるぐる。
主張するように「ふーん」と鳴くのも初めてかもしれない。
普段自己主張のない子なので よほどしんどいのだと想像して切なくなる。
立ち止まった時に、耳や首のうしろをマッサージしてあげると落ち着くようだ。
ただ、正気に戻るまでは、噛まれないように気をつけなくてはならないけど。
●
その後も朦朧としながら、ぐるぐるぐるぐる。
午前5時でも、まだぐるぐるぐるぐる。
さて6時になったぞ。外に出してみようか――
まだよく目が見えてないので、ふらふらと倒れこみ、おしっこはしない。
家に戻ってご飯を用意すると、よかった、食べたそうな顔してるぞ。
――はい、がつがつ完食! すばらしい!
ホリゾンもフードに混ぜた

てんかん薬のゾミサミドに加えて、先生の指示通り鎮静剤(抗不安薬)ホリゾンもフードに混ぜた。
上の写真が、発作後に与えるよう処方された、ホリゾン。
5mgを、朝夜1錠ずつ与える。
●
午前8時半ごろ、何十週目かのぐるぐるでやっとおしっこをした。
すごい量――、ごめんね 我慢してたのかな。
午前9時 病院に電話して指示を仰ぐ。
落ち着き始めたこと、薬も飲めたことから判断して、しばらく様子を見て、再度お昼に電話するようにとのこと。
病院に行くことが発作の引き金になることがあるので、落ち着いていたら無理しないように、との配慮である。
●
今はサークルでやっと横になった
やっぱりしんどそうな顔 可哀想でならない。
見守るつもりが私も隣でうとうとしてしまった。
ふと気づいてろくすけを見ると 寝てはいるものの目はパッチリ開いてて
私を見ている。
あっ、ごめんごめん。
ろくすけはまだ神経が高ぶっているようだけどいつもの優しい穏やかな目だ。
●
昼になり病院に電話して、引き続き落ち着いてることを伝えると、しばらく鎮静剤ホリゾンを継続して再度指示を受けることになった。
やれやれ、そろそろおしっこが出るころかな?
午後4時、やはりおしっこをいっぱいした。
●
脱水がコワイので、どんどん水を飲ませておかなければならない。
癲癇の発作が起きるようになってからは、ドライフードにウェットフードをトッピングし、水でふやかしてあげることが習慣になった。
●
癲癇は発作が連続して起きる重責発作になると、命の危険に及びかねない。
現在は「発作が起きませんように」でなく、「連続で起きませんように」に変わっている。
今晩は大丈夫でありますように。
――突然の発作に驚いた(5/6)つづく――
作:きづあすか
▶きづあすか:作品一覧
Follow @KIZASKA
――次話――
1章の最終話。
昼の発作。前回から約3か月。
発作が起きない最長記録を更新しかけていたのに――
すぐにサークルに誘導、介抱する手順は手馴れたが、見守る気持ちに慣れはない。
ろくすけ、不安そうな表情。
次の発作はいつだろう?
飼い主は祈るだけだ。
――前話――
初めて昼に発作がきた。
しかし、幸い軽症だった。
頭を高くしてやり、徘徊しても良いようにサークルをセット。
何度か経験をすると、いちいち驚かなくなるし、手際も良くなる。
――ショックではあるけれど。
気付け薬は、ごはん。
食いしん坊に感謝!
●
この記事は、下記のまとめ読みでもご覧になれます。
この記事は、下記の週刊Withdog&Withcatに掲載されています。
●
――この章の1話目です――
深夜、突然の癲癇初発作
痙攣が止まると、吠えた。
「ワオーン ワオーン ワオーン」
1分以上も。
本人は何が起きたのかわからず、パニック状態なのだ。
そして、よたよたと起き上がると、
歩く、歩く、歩く
これが、ろくすけの闘病の始まりでした。
●
――この連載の第1話です――
今日から、きずあすかさんの愛犬、ろくすけ君の闘病記を連載します。
病名は癲癇。ある日突然に発症しました。
「あの病態は、飼い主の心を乱します」
その言葉に、経験者の方は皆うなずくことでしょう。
初回は、闘病記を残す理由です。
●
闘病を考える
愛犬の闘病で悩む飼い主さんは多い。
それは見えない不安が、心にのしかかるから。
これからどうなる? いつまで続く? 医療費は?
見えないものは仕方ない。しかし、見えているものはある。
不安に怯えるのではく、どうか前向きに。
●
闘病記のヒント
闘病の奇跡は呼び込むもの
闘病記を読むと、奇跡的に治るという表現に時々出会います。
しかし奇跡は、待っていて起きるものではありません。
奇跡が起きる確率は、努力で上げることができます。
医師まかせにせず、とにかく情報を集めて分析する事です。
その中に、もしかすると答えがあるかもしれません。
セカンドオピニオンと二次診療
街の獣医師の技術と経験には大きな差があります。知識にも差があります。
なぜなら街の獣医師は、内科医であり、外科医であり、犬や猫だけでなく、ネズミも鳥も診察するのが役割です。病気ごとの専門医ではないのです。
セカンドオピニオンと二次診療は、街の獣医師の足りない部分を埋める、重要な手段と言えます。
●
出典
※本記事は著作者の許可を得て、下記のブログを元に再構成されたものです。