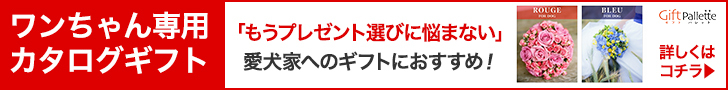闘病記の意義を考える
闘病には戦略的な視点も必要

Review
カテゴリー:コラム
作者:高栖 匡躬
闘病記が闘病の役に立つと気付いたのは、愛犬ピーチー2度目の大病(劇症肝炎)を患ったときでした。
死の淵に立つピーチーのために、少しでもと医療情報を集めたいと思うのですが、いくらインターネットで調べても、ピーチーにマッチする情報は見つかりません。
そんなときに、励ましをもらったのは、見知らぬ誰かが書き残してくれた闘病記でした。
同じ病気の闘病記はありませんでしたが、違う病気でも、闘い抜いた飼い主さんの考え方には共感ができました。絶望しそうになったときの気持ちの立て直し方は、闘病記が教えてくれたように思いますし、いざという時の覚悟もそこから学びました。
本記事は筆者自身が闘病記を読んで気付いたことをまとめた、アドバイス集のようなものです。
【目次】
- 闘病記の意義を考える闘病には戦略的な視点も必要
- はじめに - 闘病記について
- 闘病記の意義
- 闘病の中にもある効率と戦略 ~闘病、新しい視点~
- 飼い主達が闘病記を残す理由
- 闘病とペットロス|おすすめのまとめ読み
はじめに - 闘病記について
インターネット上には沢山の闘病記が存在しています。
しかしどの闘病記もが役に立つわけではありませんし、全ての部分が参考になるわけでもありません。何しろ闘病記は時間軸に沿って書かれていくので、読み物としてみると冗長であるし、未整理で余計な枝葉も多いのです。
●
本記事は『闘病記の意義』と『闘病の中にある戦略』という、2つのシリーズ記事で構成されています。闘病記をより役立てるための、使い方マニュアルのようなものを目指して書きました。
『闘病記の意義』について
このシリーズ記事は、闘病記の持つメリットや機能を整理したものです。”何のために闘病記を読むのか”をはっきりと認識しておくことで、闘病記はより効果を発揮します。
『闘病の中にある効率と戦略』について
このシリーズ記事は、闘病記から得た情報を実際に治療に活かす時の、具体的な手段についてまとめました。中でもセカンドオピニオンと二次診療、高度医療の3つのキーワードは、選択するしないは別として、治療計画を立てる際の基準になると考えています。
闘病記の意義

1話(1/2)|なぜ飼い主たちは闘病記を読むのか
医学書や論文を読むよりも現実的な情報源
犬が病気になった時、幾ら探しても、役に立つ医療情報が見つかりませんでした。
通り一辺倒だったり、逆に専門的過ぎたり。
どれもこれも、現実的ではないのです。
そんな中、飼い主が書いた闘病記に行き当りました。
動物医療の専門家ではない、普通の飼い主が書いた闘病記です。
そこからは、本当に色々な事を教わりました。
●
2話(2/2)|失敗のケーススタディでもある闘病記
選択肢を増やす有効な手段
犬や猫の闘病は、掛かりつけの獣医師に全てを委ねることになりがちです。
しかし、一旦立ち止まって、良く考えてみてください。
1つの病気には、色々な診立てがあり、治療法があります。
誰かが残してくれた闘病記を、ケーススタディとして捉えれば、選択肢は大きく広がっていくのです。
闘病の中にもある効率と戦略
~闘病、新しい視点~

1話(1/3)|闘病の奇跡は呼び込むもの
努力は、奇跡の確率を上げるもの
闘病記を読むと、奇跡的に治るという表現に時々出会います。
しかし奇跡は、待っていて起きるものではありません。
奇跡が起きる確率は、努力で上げることができます。
医師まかせにせず、とにかく情報を集めて分析する事です。
その中に、もしかすると答えがあるかもしれません。
考え方を変えれば、飼い主が愛犬や愛猫の闘病で出来ることは、それ以外には無いのかもしれません。
●
2話(2/3)|セカンドオピニオンと二次診療
医師も病院も飼い主の選択肢
ペットの闘病では、セカンドオピニオンと二次診療を、有効に活用するのが良いと思います。
街の獣医師の腕には大きな差があります。知識にも差があります。
街の獣医師は内科医であり、外科医であり、犬や猫だけでなく、ネズミも鳥も診察するのが役割です。病気ごとの専門医ではないので、腕や知識に差があるのは、当然の事なのです。
セカンドオピニオンと二次診療は、街の獣医師の足りない部分を埋める、重要な手段と言えます。
●
3話(3/3)|高度医療という選択肢
日進月歩の動物医療
動物にも高度医療があります。
それは人間で実績のある治療を、いち早く動物医療に転用するものです。
昨日治らなかった病気が、今日は直るかもしれません。
費用は掛かりますが、高度医療は病気を治す手段としては有効な選択肢です。
我が家では愛犬ピーチーが、2度それで命拾いをしました。
飼い主達が闘病記を残す理由
ろくすけの闘病記|わたしがこの闘病記を書き始めた理由
今日から、きずあすかさんの愛犬、ろくすけ君の闘病記を連載します。
病名は癲癇。ある日突然に発症しました。
「あの病態は、飼い主の心を乱します」
その言葉に、経験者の方は皆うなずくことでしょう。
初回は、闘病記を残す理由です。
その日がくるまで生きようず!|わたしが、闘病の記録を残そうと思った理由は
脚本家・波多野都さんの愛猫、ソーニャの闘病記。
なぜ闘病記を書き始めたのか?
その理由は、多くの飼い主さんが闘病記を綴る理由を代弁しています。
皆、こうして書き続ける。
そうだよね、生きようず!
その日はいつかくるけれど。
●
本記事は筆者が愛犬の闘病の際に、幾つもの闘病ブログを呼んで、感じたことをそのまま書いたものです。言うならば本コラムそのものが、1つの闘病記のようなものでもあります。
ドッグイヤーとは良く言ったもので、犬の時間は全てが早回しです。
歳をとる速度だけでなく、病気の悪化も、回復も早回しなのです。
飼い主があれこれと悩んでいるうちにも、時間は過ぎ行きます。判断に迷い、1日が過ぎるだけで、犬にとっては数日分の時間が流れることになるのです。
これから闘病に臨まれる飼い主さんは、どうか他の飼い主さんが1歩先にしてくれた経験(特に失敗談)を参考になさってください。
後悔のない闘病をなさることをお祈りします。
――高栖匡躬 ――作:高栖匡躬
解説:高栖匡躬
▶プロフィール
▶ 作者の一言
▶ 高栖 匡躬:犬の記事 ご紹介
▶ 高栖 匡躬:猫の記事 ご紹介
Follow @peachy_love
●
闘病とペットロス|おすすめのまとめ読み
ピーチー最後の闘病記|プロローグ
我が家のピーチーは肺がんでした。
爽やかに駆け抜けた一生だったと思います。
今回は前文として、
看取りの記録を残す意義などを――
犬も猫もただ去っていくのではく、何かを残していきますね。
それは、きっと悲しみではないと思うのです。
『虹の橋』『犬の十戒』『犬猫は天国に行ける?』
犬や猫の飼い主には、『虹の橋』は定着しましたね。
『犬の十戒』もそうです。
良い詩だと思うのですが、筆者は少しだけ違和感を覚えました。
その理由を探ったシリーズ記事です。
ピーチー、お前は今どこにいる?
楽しくしてるよな?
みんな幸せだったかい?
犬や猫を飼った方なら、必ず一度は思うこと。
『うちに来て幸せだった?』
病気になったり、亡くなったりするとなおさらです。
『もし、よその子になっていたら』
でもね、その答えは決まっている。最初から。
『うちの子は、幸せだったよ』
――きっとね
ようこそペットロス
ペットロスに悩む方は多いでようです。
誰もが経験することですが、”別れ”をどう捉えるかで、それは重かったり、軽かったりするように思います。
ペットロスは、必要以上に嫌うこともないように思います。
そんなコラムやエッセイをまとめました。