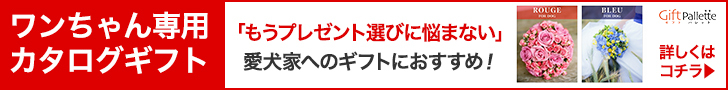チョコラッの闘病記 第4章(1/22)

本記事は長期連載の1部。そしてチョコラッは3年目(2019年6月)を迎えて生存中です。
難病であっても希望を持ち続けたいと願う、飼い主の思いで書かれた闘病記です。
初回記事はこちらです。チョコラッの闘病記 1話
ペットに貧血の症状が現れ改善しない|非再生性免疫介在性貧血と診断された|治る見込みは?|治療法は?|どんな闘病になるのか心配|免疫系疾患の難しさを実感している|経験者の体験談が聞きたい
5月6日 発病から半年
チョコラッは、非再生性免疫介在性貧血の発病から半年が過ぎました。
この病気は1年生存率が約5割。つまり、もうその半分を過ぎてしまったということです。
これから先チョコラッは、5割の壁を越えられるでしょうか?
そしてそれを越えて、もっと先まで行けるでしょうか?
●
チョコラッ2週間ぶりの血液検査行ってきました。
結果から先に言うと、良くない・・・
※通常の値は37〜
このPCVは少し下がったとは言え、横這いと思っていいと主治医から言われました。
問題なのはこちら。
※基準値 10.0~
RETICは赤血球の赤ちゃんだから、これが下がると赤血球が出来ず、PCVが下がる→貧血が進む。
今2.5って・・・赤ちゃんほぼいないじゃん!!
来週の血液検査、確実にPCV下がるじゃん!!
●
ガンマガード入れた直後は、RETIC455.4まで上がった。
ガンマガード入れたのが3月29日。
ガンマガードの効果は1ヶ月しかないと聞いてたから、5月6日の今日、効果は完全に切れたと言える。
●
ガンマガードの効果が切れる頃に、新しく始めたお薬アトピカが効いてくる予定だったんだけど。
「アトピカの効果が出てないってことですか?」って聞いたら、
「まだはっきりとは言えないです」って。
2度目のガンマガードはあり得る?

お薬変えずに1週間後にまた血液検査予定。
アトピカは2週間から1ヶ月で効果が現れる。
チョコラッは既に1ヶ月と1週間飲んでる。
それでRETICが2.5じゃ、これから効果が出るとは思えない……
●
今はね、PCV基準値に達しないものの30超えてるから元気。食欲もあるし、ちょっとなら歩くし、歯茎は薄っすらピンク。
でも、これからどうしよう。
確実に貧血が悪化することは分かってるから、また次の選択肢を考えなくては。
●
新しいお薬にするのか、輸血するのか、臓器の一部摘出とかもネット見るとあるらしいけど。それは最後の最後の選択肢なのかな。
ガンマガードは一度入れると抗体が出来て2度目からは拒否反応起こす率が高く、リスクが高すぎる。それでも2回目やる子もいるらしいが。
飼い主の気持ちは
どうしよう。
その言葉だけが頭をグルグル回る。
悩んでも仕方ないんだけど。
●
元気玉下さい( i _ i )

お願いだから元気玉下さい。m(__)m
チョコラッはまだまだ頑張るから。
家族皆んなで頑張るから。
――【非再生性免疫介在性貧血】1年生存率5割って(1/22)・つづく――
文:らぶプー
▶らぶプー:他の作品一覧
――次話――
免疫系の貧血は、免疫介在性溶血性貧血と、非再生性免疫介在性貧血に別れています。
前者は赤血球を自分の免疫が壊してしまう病気。
後者は赤血球が作りだせなくなる病気。
両方難病だけれど、後者の方が症例が少なくいために、対応が難しいんです。
――前話|前シリーズの最終話――
血液検査の結果は良好。
免疫抑制剤の効果が出て来た?
生命の危機を、また一つ乗り越えた?
今の医療では完治する病気でないけれど、それでもほっと一息の飼い主でした。
●
この記事は、下記のまとめ読みでもご覧になれます。
この記事は、下記の週刊Withdog&Withcatに掲載されています。
●
――この連載の最初の記事です――
この病気は、自己免疫不全で起きるもの。
自分の免疫が、自分の体を攻撃し始めるのです。
病原菌やウィルスが見つかるわけでもなく、CTやMRIにも病変が映りません。
だから、最初はそうだと分かりません。
なんとなく調子が悪い……
病院に行っても原因不明。
しかし、状況は悪化していく。
何故――、それが始まりです。
まずは病名が確定するまでのお話から。闘病記を書く理由についても語られます。
●
ペットの闘病についてのヒント
闘病の奇跡は呼び込むもの
闘病記を読むと、奇跡的に治るという表現に時々出会います。
しかし奇跡は、待っていて起きるものではありません。
奇跡が起きる確率は、努力で上げることができます。
医師まかせにせず、とにかく情報を集めて分析する事です。
その中に、もしかすると答えがあるかもしれません。
セカンドオピニオンと二次診療
街の獣医師の技術と経験には大きな差があります。知識にも差があります。
なぜなら街の獣医師は、内科医であり、外科医であり、犬や猫だけでなく、ネズミも鳥も診察するのが役割です。病気ごとの専門医ではないのです。
セカンドオピニオンと二次診療は、街の獣医師の足りない部分を埋める、重要な手段と言えます。
●
出典
※本記事は著作者の許可を得て、下記のブログを元に再構成されたものです。