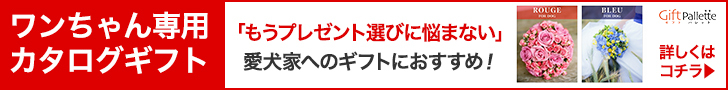ようこそペットロス(2/4)

別れの準備を考える
ペットロスのお話、2回目です。
前回は飼い主が、愛犬の老いを意識するようになるまでの過程を書きました。
ここから先は、飼い主さんごとに考え方が違ってきます。
愛犬の老いの先に、避けられない死を明確にイメージした飼い主さんは、別れの準備をはじめることでしょう。その方法は、飼い主さんごとに様々です。
●
死をイメージしない飼い主さんは、別れの予感は”縁起でもない”ものとして、意識からなるべく遠ざけることでしょう。目の前で弱っていく愛犬がいても、それと死が直結しないわけです。この気持ちもとても良く分かります。
死をイメージする/しないは、カードの表裏で、実は同じことを意味しているように思います。
ペットロスは愛犬が生きているうちに始まるのかも

自分の経験に照らすと、愛犬の死をイメージした時点から、ペットロスが始まったように思います。亡くなっていないのにペットロス? と思われるかもしれませんが、死を明確に意識した時点から、心は悲鳴を上げはじめるのです。
結局ペットロスと言うのは、愛犬が死んでから引き受けるのか、死を意識した時点から少しずつ引き受けるのかの違いなのかもしれません。
今振り返ると、筆者は8つの段階を1つ1つ噛みしめるようにして、”その時”の覚悟を決めて行きました。意識していたわけではありませんが、恐らく1つずつそれらを消化していったことが、ペットロスを軽くした要因であると思っています。
●
ここからは、筆者がどのように別れの準備をしていったかを書こうと思います。誰にも当てはまるものではないと思いますが、普遍的な内容も結構あるように思います。
尚、これから書くことは、こうしなさいという指南ではありませんので、読んでみて”これは”と思うことがだけ、実践されると良いと思います。
●
最初に、ピーチーの病気の推移を書いておきます。
ピーチーの命を奪ったのは最終的には肺がんでしたが、それに至る前の段階で、自己免疫不全による劇症肝炎我を発症。幸いそれは完治したのですが、バランスを崩した体はなかなか回復しませんでした。
リハビリをしながら、ゆっくり元に戻していこうとするのですが、ある時を境に筋肉は落ちていく一方でした。
●
「これは普通ではないな」
そう感じたことが、別れの予感であり、別れの始まりだったように思います。
次項から病状の進行に沿って、別れの準備を書いて行きます。
闘病の初期(予感の始まり)

この頃はまだ病状は深刻ではありません。散歩も毎日行っていた時期です。
弱ってはいたので、以前の半分の距離を、倍の時間を掛けて歩いていました。
前述の「これは普通ではないな」という思いが芽生え始めた頃です。
●
①全てを受け入れて、楽しむことにしました
最後の闘病では、愛犬の体は階段を下りるように下降していきます。
「もしかしたら、奇跡的に回復するのでは?」
そんな思いは、日に日にしぼんで行きました。
「恐らく、もう元の体に戻る事はないだろう」
実感としてそう思うようになりました。
ただし、諦めたのとは違います。冷静に観察をした結果としてそう思いました。
長年見続けている愛犬だから、感じることでもありました。
●
そこでまず考えを変えました。
回復しないのならば、出来なくなった事を嘆くのではなく、出来る事が沢山残っていることを喜ぼうと思ったのです。
「目の前で起きる事を全て受け入れる」
そう決めた途端に、視界が開けたように思いました。
闘病の中期(予感が確信に変わる時期)

愛犬がだんだん弱っていく姿を見るうちに、予感として感じていた別れは、逃れようのない現実だと思うようになりました。
最初のうちは、「考えないようにしよう」と思うときもあったのですが、それでは駄目だと思い直しました。全てを受け入れるつもりでしたし、そのためには現実を直視しなければならないと思いました。
●
②別れをが近いことを、明確に意識しました
この調子では、あと3年一緒にはいられないな。
2年はどうかな? 多分無理なんじゃないかな。
次の夏は越えられるかな?
一つ一つを具体的に考えていくと、別れが遠くない事を実感します。
実感するのは、嘆くためではありません。
現実を知ることではじめて、「それならば、今、何をやる?」という気持ちになれるのです。
●
ピーチーを送った今、改めて思うことがあります。
それは、後悔の念というものは、飼い主の心からずっと消えることはないだろうということです。具体的に言うと、それは何かをして上げなかったことに対しての、心残りのように思います。
先にも書きましたが、筆者はピーチーとの別れに満足しています。だから大きな後悔はありません。
――しかしそれでも尚、ちょっとした悔いは残っているのです。
●
どんな悔いかというと、次の2つです。
(まだ歩けて)散歩したがっていたときに、忙しくて連れて行けない日があった。
(まだ食欲があった最後の日に)食べたがっていたおやつを、一度にあげないで次の日に取っておいたこと。
――次の日はもう食べられませんでした。
●
些細なことだと思われるかもしれませんが、この2つはどうしても心の中から消えません。きっと愛犬の生前にどんなに手を尽くしてあげたとしても、飼い主の心の中には何がしかの悔いが残ってしまうものなのでしょう。
だとしたら――
それをなるべく少なくした方が、良いのだと思います。
そのためには――
今できることがあるのなら、今やりつくすしかありません。
だからこそ――
つらくても現実を見て、残された時間を、はっきりと意識しなければなければならないと思うのです。
闘病の後期(終末期の手前)

闘病が後期になってくると、頭で理解していた愛犬との別れを、肌で感じるようになります。それは多分、愛犬の方もそうなのだと思います。
ピーチーとは言葉を交わせませんでした。だからピーチーの気持ちは確認のしようがないのですけれど、あの頃の目は何か悟ったかのようであり、何かを予感しているように見えました。きっと愛犬を看取った経験のある方は、同じように感じられたのではないでしょうか?
下記の2つは、この時期に思ったとこです。
●
③別れを、”死”と理解するようにしました
別れ=死なのに、それを考えたくないために、オブラートにつつんで考えてしまうのが飼い主の人情です。筆者もはじめのうちはそうでした。
あるとき、頭の中にある”別れ”という言葉を、”死”と言い直してみました。そうすると、別れは急に現実のものとなり、とても切実なものになりました。
死を思うことで、②に書いた残された時間や、そこでやってあげるべきことを、より意識できるようになったと思います。
それからは、ブログでの闘病記を書く際には、読まれる方の心情に配慮して”別れ”という言葉を使いましたが、頭の中は常に”死”という言葉に変換をしていました。
●
④思い出を作っていることを意識するようにしました
その頃に考えたことがもう1つあります。
ピーチーが去ってしまった未来から振りかえると、きっと今現在は思い出なのだということです。今考えている事も、今行っている事も、いつか全て思い出に変わり、そしておそらく未来になって、何度も何度も思い出すに違いないのです。
だとしたら、良い思い出を振り返りたいものだと思いました。
おもしろいことに、そう考えると今の自分が客観視できるようになりました。
「”今”は、将来の自分への贈り物のみたいなものだな」
そう考えると、気持ちが軽くなりました。。
● ● ●
こんな風に筆者は、1つ1つ小さな覚悟を決めていきました。
多分、一度には引受けきれない思いを、少しずつ消化していったのだと思います。
8つの段階の覚悟。
残りの4つは次回の記事にて。
――別れの後先・飼い主が出来ること(2/4)・つづく――
文:高栖匡躬
▶プロフィール
▶ 作者の一言
▶ 高栖 匡躬:犬の記事 ご紹介
▶ 高栖 匡躬:猫の記事 ご紹介
Follow @peachy_love
●
――次話――
「その日」は迫ってきます。
それは肌で感じることができます。
まずは、悲しまないと決めました。
安心して逝かせてやりたい。だとしたらどうしたらいい?
苦しませたくはない。だから安楽死は受け入れよう。前向きな手段として――
そうやって覚悟を積み上げて――
最後は、笑顔で送ってやりました。
我が家の体験談です。
――前話――
ペットロスは誰もが経験するものです。
それで悩む方が多いものでもあります。
筆者のペットロスは、比較的軽かったと思います。
むしろ――、それを楽しんだのかも。
なぜそうだったか?
それを考えた記事です。
ちょっとは参考になるかもしれません。
●
この記事は、下記のまとめ読みでもご覧になれます。
●
別れは特別なものでなく
命を預かる本望
ペットの闘病は、全てにおいて飼い主の選択に委ねられますね。
治療をする/しないに始まり、どんな治療法を選ぶのかまで。
筆者の愛犬ピーチーの3度めの闘病は、『闘わない』という選択をしました。
他の選択肢はゼロではありませんでした。
しかし、敢えて闘わないことにしました。
●
別れについて考える・エッセイ
ラフと歩いた日々|全3話
愛犬を看取る、家族のお話。
ペットと暮らす者なら誰もが通る道だけれど、少しずつ違う道。
色々な選択肢があって、正解は一つではない。
わが家なりの送り方って何?
『ラフと歩く日々』の続編です。